副業ブームが広がる中で、「自分も副業を始めてみたけど、確定申告って本当に必要?」「20万円以下なら何もしなくていいって聞いたけど…」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
実は、副業を始めると想像以上に「税金との付き合い」が増えてくるんです。特に確定申告について正しく理解しておかないと、思わぬ税務トラブルに巻き込まれたり、会社にバレてしまうリスクもあるんですよ。
このページでは、副業初心者でもすぐわかる確定申告の基本から、よくある誤解やバレないための工夫、青色申告による節税方法までをわかりやすく解説していきます。
副業でも確定申告が必要なケースとは?
副業を始めたばかりの方の多くが、「そもそも確定申告って自分も必要なの?」と疑問に思うのではないでしょうか。会社員として本業がありながら副業収入がある場合でも、条件によっては確定申告が必要になります。ここでは、まずどんなケースで確定申告が必要になるのかを詳しく見ていきましょう。
副業の所得が年間20万円を超える場合
最もよく知られている基準が、「副業所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要」というルールですね。ここでいう「所得」とは、売上(収入)から経費を差し引いた金額を指します。
給与所得と雑所得の違い
副業の種類によって「所得の区分」が異なります。たとえば、アルバイトやパートなど雇われる形の副業は「給与所得」、自分で業務を請け負うようなライター・デザイナー業などは「雑所得」または「事業所得」として扱われます。申告方法も変わってきますので要注意です。
住民税だけでも申告が必要なケース
「所得税は発生しないから大丈夫」と思っていても、実は住民税の申告が必要なケースもあります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の課税対象になる場合、住んでいる市区町村に「住民税申告書」の提出が必要なんですね。
専業主婦・学生・年金受給者の申告義務
専業主婦や学生、年金受給者などであっても、副業で得た所得が一定額を超えた場合には確定申告が必要になります。収入が少ないから大丈夫と思っていても、控除対象外になると申告義務が発生することがありますので確認が必要です。
確定申告が不要なケースとは?
逆に、年間所得が20万円以下で、他に申告義務がない人であれば、確定申告を行わなくても問題ない場合もあります。ただし、この「20万円以下ルール」には落とし穴もあるので、次章で詳しく解説します。
20万円ルールの誤解と落とし穴
副業初心者にとって、「20万円以下なら申告不要」と聞くと、つい安心してしまいますよね。でも実際は、さまざまな誤解があるのも事実です。
所得と収入の違いに注意
よくある間違いが、「副業収入が20万円以下だから大丈夫」と思い込んでしまうこと。ここでの判断基準は「所得(収入-経費)」なので、経費の把握が不十分だと申告漏れになることも。
経費を差し引く前の金額ではない
売上ベースで「20万円以下」と判断するのはNGです。たとえば、売上が50万円でも経費が35万円なら所得は15万円となり、確定申告不要となる可能性があります。
所得税と住民税の扱いの違い
20万円ルールは「所得税」の話ですが、住民税のルールには適用されません。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要というパターンもあるため、注意が必要です。
複数の副業収入がある場合の合算ルール
メルカリ・ウーバー・ブログ収入など、複数の副業収入がある場合は、すべて合算して20万円を超えるかを判断します。個別に20万円未満でも合計して超えていれば申告が必要です。
バレる理由と課税リスク
「バレないだろう」と思って申告しなかった場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。特に、住民税の情報から会社に知られるケースが多いため、申告はしっかり行うのが安心ですよ。
副業の確定申告のやり方【ステップ別】
ここからは、実際に確定申告を行う方法をわかりやすくステップでご紹介します。
必要書類と準備物一覧
- 源泉徴収票(本業)
- 副業の収入を示す書類(報酬明細、通帳記録など)
- 経費の領収書
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
- 銀行口座情報(還付用)
所得区分の確認と仕訳
副業が「雑所得」か「事業所得」かを明確にし、それぞれに応じた収支内訳書や青色申告決算書を準備します。
経費の計上方法と注意点
副業に関する通信費、交通費、機材購入費などは経費に計上可能です。ただし、プライベートとの共用部分は按分(あんぶん)計算が必要です。
白色申告と青色申告の違い
白色申告は簡単な記帳で済む一方、青色申告は要件を満たせば最大65万円の控除が受けられます。節税したいなら青色がおすすめです。
e-Tax・郵送・持参の3つの提出方法
提出は以下の3つから選べます:
- e-Tax(インターネット申告)
- 郵送(税務署宛に書類を送付)
- 税務署に直接持参
e-Taxならスマホからも申告可能なので便利ですよ!
提出期限と延滞リスク
申告期間は毎年2月16日〜3月15日ごろ。期限を過ぎると「無申告加算税」「延滞税」がかかることもありますので要注意です。
バレない?住民税・所得税からわかるリスク
「副業が会社にバレないようにしたい」と考える人は多いですよね。では、実際にバレる仕組みを理解しておきましょう。
会社にバレる原因は「住民税」
多くのケースで会社にバレるきっかけになるのが、住民税の通知です。副業分の住民税が合算されて高くなると、会社が不審に思う場合があります。
普通徴収と特別徴収の違い
住民税の納付方法には「特別徴収(会社が天引き)」と「普通徴収(自分で支払う)」があります。副業分を普通徴収にすれば会社にバレるリスクを下げられます。
「普通徴収」にする方法と手順
普通徴収にするのは簡単です。確定申告時に「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付」を選択するだけでOKです。忘れがちなので、最後までしっかりチェックしてくださいね。
税務署からの通知が来るケース
稀にですが、税務調査や書類確認の一環として税務署から会社へ照会がある場合もあります。普段から適切な申告を心がけておくのが一番です。
所得税は会社に通知されるのか?
所得税は基本的に個人ベースで完結するので、直接会社に通知されることはありません。ただし、住民税の連動により間接的に知られるリスクはあります。
青色申告と白色申告の違い
副業の規模が大きくなってきた方には、青色申告を検討するのもおすすめです。
青色申告のメリット
- 最大65万円の所得控除
- 赤字の繰り越し(最大3年間)
- 家族への給与が経費にできる
など、メリットが多く節税効果も高いです。
青色申告の申請方法と期限
青色申告を行うには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請期限は、原則として開業から2か月以内です。
複式簿記と単式簿記の違い
65万円控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要です。難しそうに見えても、会計ソフトを使えば初心者でも安心ですよ。
65万円控除と10万円控除の違い
簡易簿記で青色申告をする場合は10万円控除となります。しっかり節税したいなら、複式簿記での65万円控除がおすすめです。
会計ソフトの活用で申告も簡単に
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、帳簿付けから申告書の作成まで自動化できます。スマホからも操作できて便利です。
よくある質問Q&A
会社にバレずに副業するには?
- 住民税を「普通徴収」にする
- 社内規定を確認しておく
- SNSや名刺で副業を公開しない
このあたりが基本の対策ですね。
バレた場合のペナルティはある?
就業規則に違反していなければ大事にはなりませんが、最悪の場合は処分や退職勧奨の可能性もあるので注意です。
副業の種類によって申告方法は違う?
はい。たとえばメルカリは「雑所得」、アルバイトは「給与所得」、ブログ収益は「事業所得や雑所得」に該当します。
副業で使ったスマホ代は経費にできる?
業務に使った割合に応じて「按分」することで、経費として一部計上できます。
マイナンバーでバレる?
マイナンバー制度で所得情報は国税庁に集約されますが、それが直接会社に通知されるわけではありません。
副業の確定申告で失敗しないための注意点
申告漏れのリスク
無申告や過少申告が発覚すると、「加算税」や「延滞税」が発生することがあります。
経費の過剰計上に注意
経費にできるからといって、私的な支出まで含めると指摘を受けることがあります。
領収書の保存義務
帳簿や領収書は、最低でも5年間(青色申告は7年間)保存する義務があります。
記帳の継続と証拠保全
日々の取引をこまめに記帳しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。
税務調査が入る可能性は?
所得が増えてきたり、経費の内容に疑問がある場合などに税務調査が入ることがあります。普段から正確に処理しておけば大丈夫ですよ。
まとめ:副業は経費を引いた金額で計算してしっかり確定申告を!
副業が広がる今の時代、確定申告は「面倒な手続き」ではなく、「自分の収入と納税をコントロールする手段」です。
正しく申告すれば、税金で損することもないですし、堂々と副業に取り組むことができますよ!

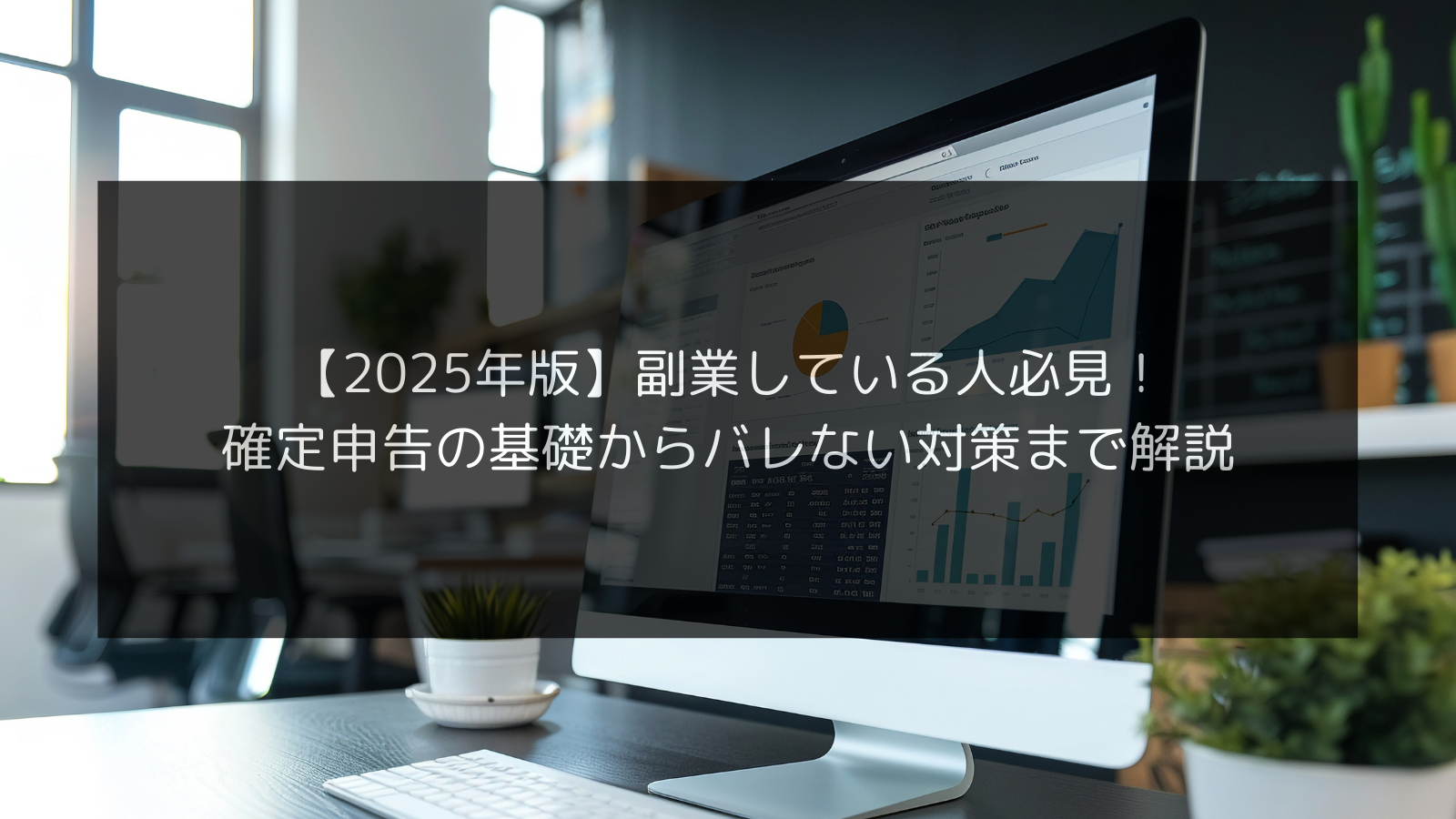
コメント